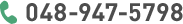秋は持久走のシーズン!
秋は持久走のシーズン!当かけっこ教室も熱が入っています。(親の方が?)
そりゃそうです。どこの親でも
- 我が子が颯爽と走る姿を観たい!
- 少しでも順位を上げたい!
- 1位を取ってほしい!
- 笑顔で楽しくゴールしてほしい!
でも持久走って本当に苦手な人が多い。
持久走って本当に辛い。いい思い出なし・・・
そんな人がほとんどかと思います。
かく言う僕も大嫌いでしたから。
ちなみに僕は高校まで陸上部でしたが短距離で長距離大嫌いでした。
でもね。
本当に楽しいんですよ!長く走れるって!
体が言うこと聞いてくれるようになるとやればやるほどハマります。
そんな体の使い方を僕自身は、常歩なみあし身体動作(2軸感覚)で学び実践し、今はそのメソッドを
かけっこ教室の子ども達や、クライアントさんに還元しています。
さて前置きほこの辺にして、
持久走を速く走るための5つのポイント
お伝えしたいと思います。
前置きしますが、こどもがきもちよく走るための内容であって持久走を専門的に捉えた内容ではありません。
練習は最低週に3回です。毎日できるなら行なってください。
①距離に慣れる
ゆっくりで良いので持久走の距離+を繰り返し走る。1km未満なら1km、1km以上なら1,2kmと、本番より少し長めに走る。
会話や歌を歌うことができるくらいのペースで慣らしてください。
メリットは距離に慣れることで本番緊張しなくなる
ゆっくり走でも続けていると心肺機能が上がる
などです。
②ペース配分(後半に力を取っておく)
基本的には前半〜中盤までは同じペースで気持ちよく走ります。
その気持ち良さはそれぞれです。苦しいけど走り続けられる子もいれば、走れない子もいますので。
気持ちの良いスピードや距離は何度も走ればわかってきます。
理想は残り3分の2あたりでペースを上げられるとかっこよくゴールできます。
③スピードコントロールは体の傾きで行う
スピードをあげようと思うとどうしても力みが先にきて、腕や足に力が入り始め、硬いフォームになり、めちゃくちゃ疲れます。
力まずスピードを上げるには胸を握りこぶし半個分前に傾けます。それだけで加速します。
これ意識しすぎると腰だけ後ろに残り、足が後ろに流れ、つんのめるようなフォームになるので、ほんの少しだけです。
それでもじゅうぶんです。体を起こせば、減速します。
最後の一踏ん張りは腕振りが有効ですけどそれはせいぜい最後の50〜100mくらいです。
※おとなに対してのアドバイスでは腰を前にとか、おへそを前に、軸足に腰をのせてていく、など表現が変ります。
④顎を引かない
よく顎を引け〜!と言うコーチの怒声を聞いたことあると思います。
疲れてくると顎が上がりますよね?で、頑張って顎を引くともうフォームガチガチ、コーチは怖い、体は動かない。
実は顎を引くと首、肩、胸の筋肉が力み、腕振りも硬くなり、全身に力みが伝わります。
見方を変えると、
辛い時は顎を上げる。つまり体はラクなフォームを選んでいると言うことなんです。
走り出して最初のうちは顎を引いていられるのは、「まだ疲れていないから無理が効いている」
と言うことなんです。
だから、最初から顎は上げていた方がラクに走れるんです。
コツ
目深かにキャップをかぶり前を見る感じです。
横から見ると耳の穴と鼻先が水平になるくらいです(これを専門的にはカンペルラインといいますが今回は割愛)
⑤腕は振らない
これは正確には腕は意識して振る必要はないと言う意味です。
振るのは肩です。肩が前後に揺れ、肩に遅れて腕がついていくのが自然な腕振りです。
走り方を教わっていない子どもたちは往々にして、肩を揺らしてうねうね走ります。
小学生のうちはそれでいいのです。姿勢をよく走れという指示は時に緊張、硬直につながります。
自然に良い姿勢が取れるようになるまではあまり気にしないことです。
競争心が芽生えてないお子さんの場合
①を続けてください。欲張らないで気持ちよく走りきることを心がけてください。
楽しく上手に走りきることで子どもたちは辛さも喜びに変えてくれます。
持久走を嫌いになるケースは
死ぬ思いをする(飛ばしすぎて後半苦しむ)
順位で自己評価をしてしまうことです。
自分なりに気持ちよく走り切ることが大切です。
苦しい練習をすれば速くなると言った、発想は持たないでください。
ストイックな練習で成績を上げる前に、体をうまく使うこと、心理的にラクにさせることで運動の質がよくなります。お子さんが楽しくゴールできるように周りがサポートして、声をかけて上げることも大切ですよ。
まとめ
①距離に慣れることでペース配分がわかる
②後半に力を取っておくとかっこよくゴールできる
③スピードコントロールは体の傾きで行い、顎を引かず腕も振らない
一つでも二つでもチャレンジして見よう!!
小学生持久走対策
《小学生向け》持久走を速く走るための5つのポイント